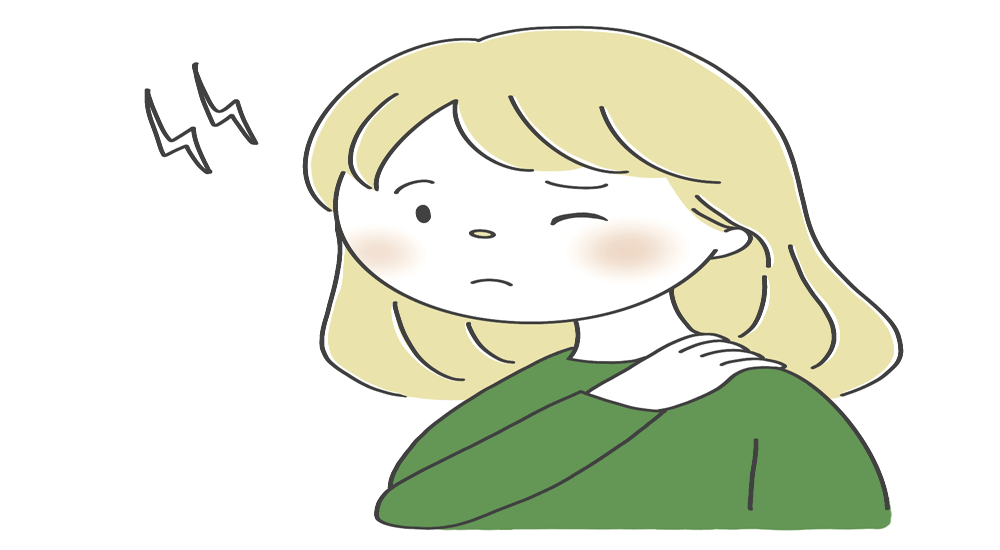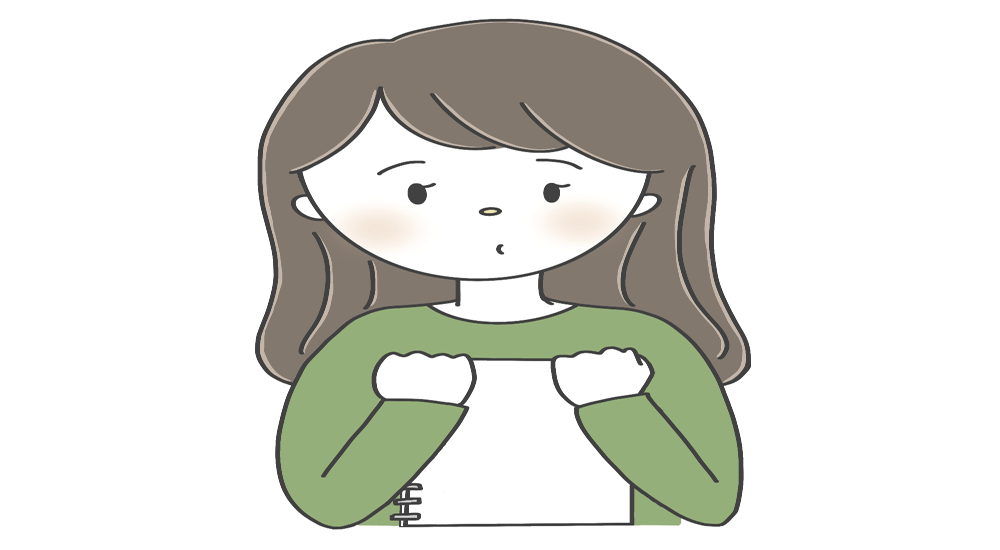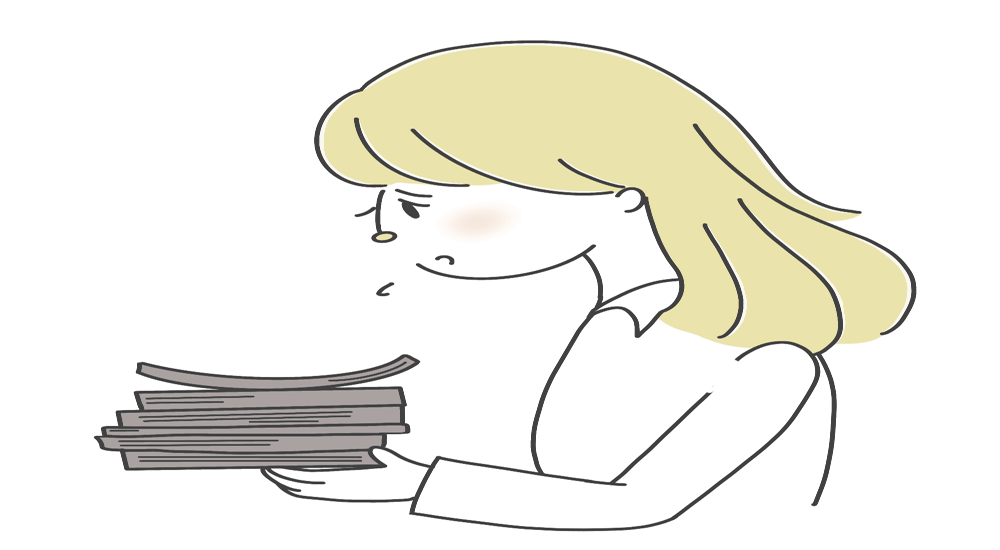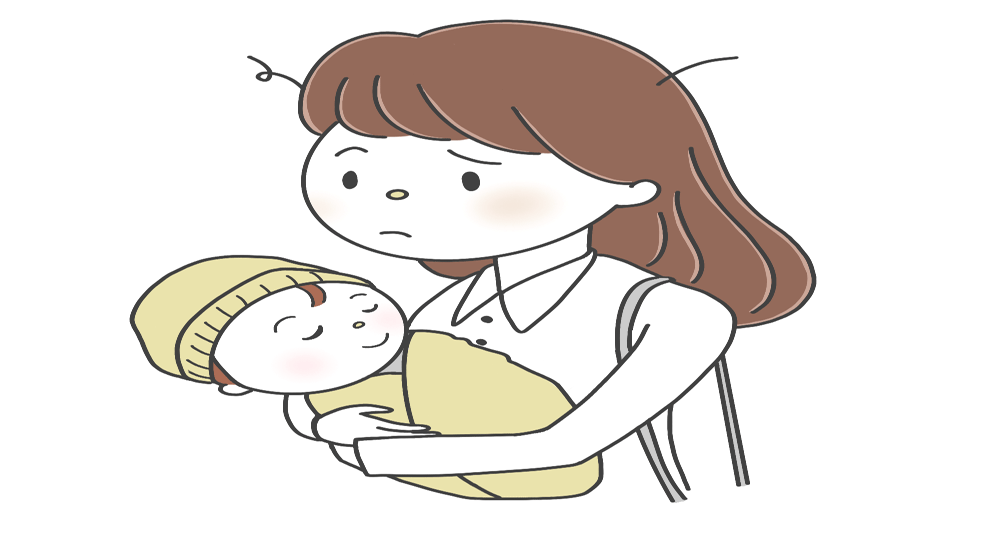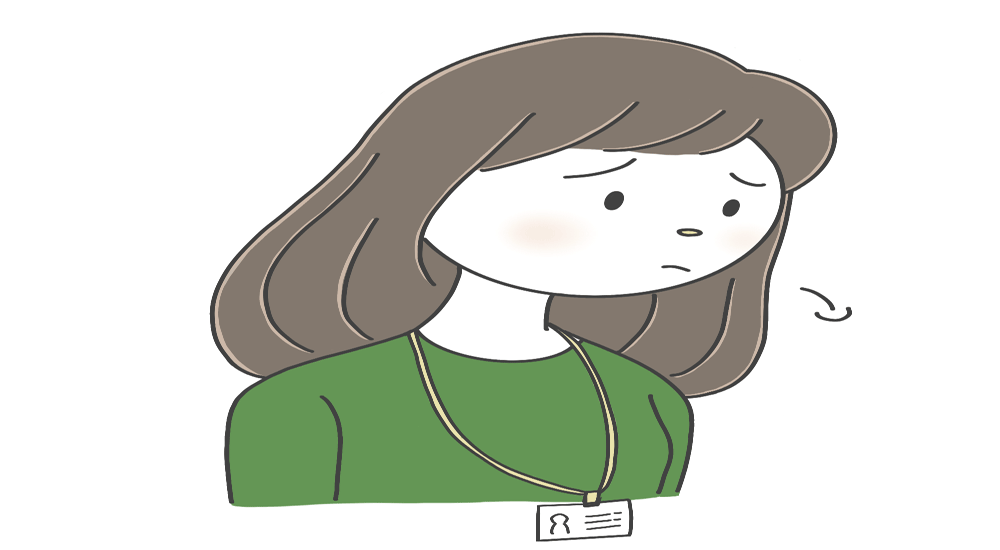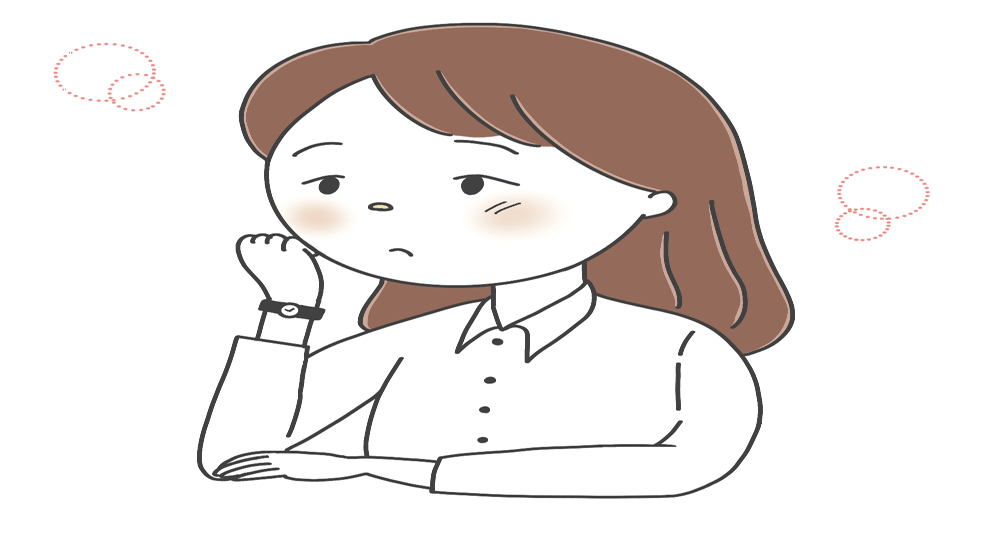welcome
「五感の癒しを追求し、精油と人間の共存を模索しながら精油の可能性・信頼性を広げていく」 「質の良いトリートメントで日々減っていく心と身体のエネルギーをチャージする」を経営理念にかかげレモンルームを主催して13周年を迎えました。 日々多くの方にご支持・ご理解を頂き誠に感謝申し上げます。
「精油と対話しながら心と身体の変化を感じることができるサロン」を目指し、皆さまと一緒になって精油がある生活を楽しんでおります。
今後も多くの方にご満足いただき、精油で効率の良い健康維持ができる内容も取り揃えて、心と身体の新しい発見ができるよう精進してまいります☆
どうぞよろしくお願い致します。
レモンルーム店長 高山久仁子
↑ 「予約・予約の確認・変更・キャンセル」がLINEで全てできます!!
まずは「お友達追加」→「お客様情報」の入力から(^^)
☆LINEで簡単予約☆
①「お友だち追加」
②「お客様情報のご入力をお願いします」↑
③「ご希望のメニュー・お日にち・開始時間をお選び下さい」
④予約内容→予約が確定しました!
⑤ご予約当日はお気をつけてお越しください(^^)
※お日にちのご変更・キャンセルは前日の18時までにLINEでご連絡下さい。
※ご予約時間の5分前にご到着下さい。
※ご予約時間に遅れる場合は必ずご連絡下さい。お時間の都合上ご希望のメニューに添えない場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※ご予約状況は日々変化しております。ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承下さい。
※キャッシュレス対応
アロマサロン&アロマスクール対象です 。(出張アロマレモン活動は対象外)
ペーパーレス化を導入しております(レシートはメールで送信致します)
決済後画面にメールアドレスの入力をお願いしております。
【YouTube動画】
アロマサロン・アロマスクール・アロマ自販機の様子です。
You Tube